目次
肥満症とは?症状・原因・治療法を医師が解説

肥満症は、単なる肥満とは異なり、肥満が原因で高血圧や糖尿病、脂質異常症などの健康障害が起きている状態を指します。日本ではBMI(体格指数)が25以上で、かつ高血圧や糖尿病などの生活習慣病を合併している場合に「肥満症」と診断されます。
放置すると、心筋梗塞や脳卒中など命に関わる病気へと進行するリスクがあるため、医師による適切な診断と治療が重要です。
肥満症とは?肥満、メタボとの違いは?
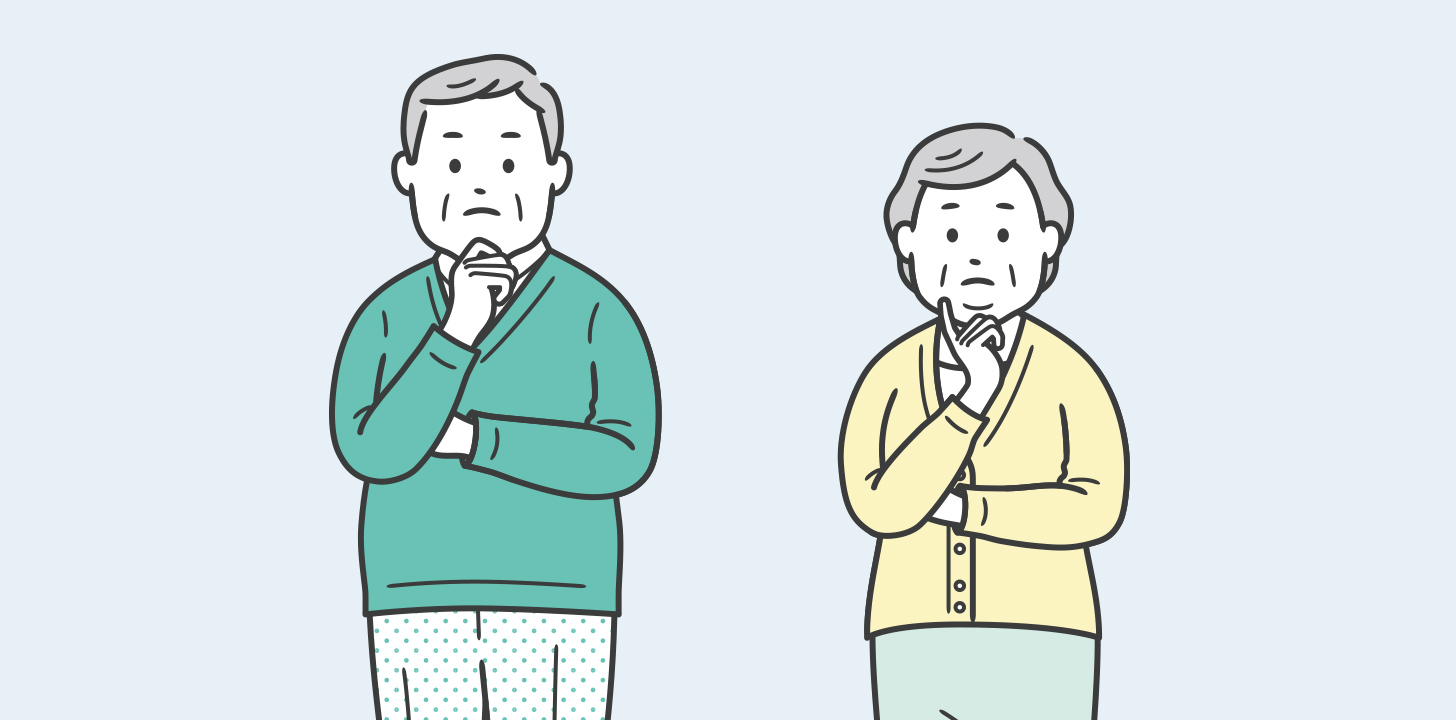
「肥満」はあくまで体格の状態を示す言葉であり、BMIが25以上であれば肥満とされます。一方、「肥満症」はその肥満が原因で何らかの健康障害(高血圧、糖尿病、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群など)を引き起こしている状態です。
日本肥満学会のガイドラインにおける定義では、BMIが25以上であり、かつ肥満に起因または関連する健康障害(高血圧、脂質異常症、2型糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、脂肪肝、変形性膝関節症など)を1つ以上有する場合に「肥満症」と診断されます。
肥満があっても健康上の問題がなければ「肥満症」には当たりません。逆に、見た目ではあまり太って見えなくても、内臓脂肪が多く生活習慣病を発症している場合は、肥満症と診断されることがあります。
また、似た言葉に「メタボリックシンドローム(メタボ)」があります。メタボは、内臓脂肪型肥満に加えて高血圧、高血糖、脂質異常のうち二つ以上を併せ持つ状態で、将来的に心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患につながるリスクが高いとされる“予備群”です。この段階ではまだ明確な健康障害が出ていないことも多く、生活習慣の見直しによって改善が期待されます。一方で、肥満症はすでに健康障害が生じており、医学的な治療が必要と判断される病気として位置づけられます。
簡単に整理すると以下のように分類されます。
| 分類 | BMI | 健康障害の有無 |
|---|---|---|
| 肥満 | 25以上 | なし |
| メタボ | 25以上(主に内臓脂肪) | 出る前〜出始め |
| 肥満症 | 25以上 | あり |
肥満症の原因
肥満症の主な原因は、エネルギー摂取量(食事)と消費量(運動)のバランスが崩れることによる内臓脂肪の蓄積です。特に以下のような要因が関係しています。
- 食べ過ぎ・高カロリーな食事
- 運動不足
- ストレスや睡眠不足
- ホルモンバランスの乱れ
- 遺伝的体質
中でも「ストレス」は重要なリスク因子のひとつです。ストレスがかかると、体内で「コルチゾール」というホルモンが分泌され、これが食欲を高めたり、脂肪を蓄えやすくしたりします。その結果、内臓脂肪が増え、肥満症のリスクが高まると考えられています。
また、内臓脂肪は炎症を引き起こす物質を分泌するため、糖尿病や高血圧などの疾患を悪化させることがわかっています。
肥満症の主な症状とリスク
肥満症は自覚症状が少ないことが特徴です。しかし、以下のような疾患を合併するリスクが高くなります。
- 高血圧
- 脂質異常症(中性脂肪やコレステロールの異常)
- 2型糖尿病
- 睡眠時無呼吸症候群
- 非アルコール性脂肪肝炎(NASH)
- 膝や腰の痛み
これらを放置すると、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気に繋がる恐れがあります。
肥満症の治療法|生活習慣の改善が基本
1食事療法
肥満症の食事療法では、「摂取カロリーを抑えつつ、栄養バランスのとれた食事」を基本とします。そのうえで、次のような点に注意すると効果的です。
控えるべきこと
- 揚げ物やスイーツ、清涼飲料水など
- 間食や夜遅い食事
- 2型糖尿病
意識してとりたい食材・食習慣
- 野菜とたんぱく質を中心に(炭水化物や脂質はとりすぎないように)
- 玄米、納豆、鶏むね肉、野菜、海藻類など、栄養価の高い食品
- 2型糖尿病
2運動療法
肥満症の治療では、有酸素運動と筋力トレーニングの両方を組み合わせて行うことが効果的です。
運動を習慣化することで、脂肪の燃焼を促すだけでなく、基礎代謝が上がり、太りにくい体づくりにもつながります。
有酸素運動(脂肪燃焼)

- ウォーキング、ジョギング、水中運動などを週3〜5回行う
- 心拍数が軽く上がる程度の運動を、無理なく継続するのがポイント
筋力トレーニング(基礎代謝アップ)
- 自重トレーニングや軽いダンベル運動で筋肉量を維持・増加させる
- 筋力がつくとリバウンドしにくい体質につながる
継続のための工夫
- 最初は1日15〜30分の軽い運動からスタート
- 無理せず続けられるタイミングや方法を選ぶ
3薬物療法(医師の判断により)
以下のような薬が使われることがあります
- 保険診療の場合、3割負担での自己負担額の目安も併記しています
| 商品名(薬剤名) | 自己負担目安(3割負担の場合) | |
|---|---|---|
| サノレックス(マジンドール) | 食物繊維や低GI食品(血糖値を上げにくい食品)を積極的にとり入れる | 約1,500〜2,000円/月 (保険適用) |
| ウゴービ(セマグルチド) | GLP-1受容体作動薬で、脳の満腹中枢に働きかけて食欲を抑え、体重減少を促進。週1回の注射で継続しやすい。保険適用。 | 約3,000〜5,000円/月 (保険適用) |
| ゼップバウンド(チルゼパチド) | GIPとGLP-1のデュアル作動薬。より高い減量効果が期待される。 | 約3,000〜5,000円/月 (保険適用) |
| アライ(オルリスタット) | 脂肪の吸収を抑える内服薬。薬局でも購入可能(要指導医薬品)。 | 自由販売:6,000〜8,000円/月 (保険適用外) |
それぞれの薬には特徴や副作用、向いている患者さんのタイプがあります。
たとえば「ウゴービ」は週1回の注射で済むため継続しやすく、「ゼップバウンド」はさらに高い体重減少効果が報告されています。「マジンドール」は短期的に体重を落としたい方に適し、「アライ」は比較的副作用が少なく、内臓脂肪の多い方に向いています。
4外科治療
肥満症の治療は、まず食事や運動などの生活習慣の改善が基本ですが、重度の肥満症で他の治療で効果が得られない場合は、外科的な治療(減量手術)が検討されることもあります。
代表的な手術には、胃の一部を切除する「スリーブ状胃切除術」や、胃と腸の流れを変える「胃バイパス術」などがあり、体重減少や合併症の改善が期待できます。
ただし、術後の生活管理が必要であり、誰でも受けられるわけではありません。希望する場合は、専門医による診察を受けることが大切です。
肥満症は、
当院へご相談ください
くまもと睡眠メディカルクリニックへ
ご相談・ご予約はこちら
肥満症に関するよくある質問
現在、このカテゴリーにはよくある質問がありません。
まとめ
肥満症は、見た目だけで判断できない「病気」です。生活習慣を整えることが最も重要ですが、必要に応じて薬物療法などの医学的サポートも受けながら、継続的な管理が必要です。ストレスや不規則な生活が原因で体重が増えてしまった方も、医師の診断と適切な対策により改善することが可能です。気になる症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

